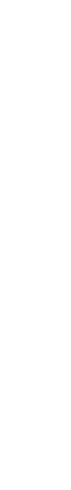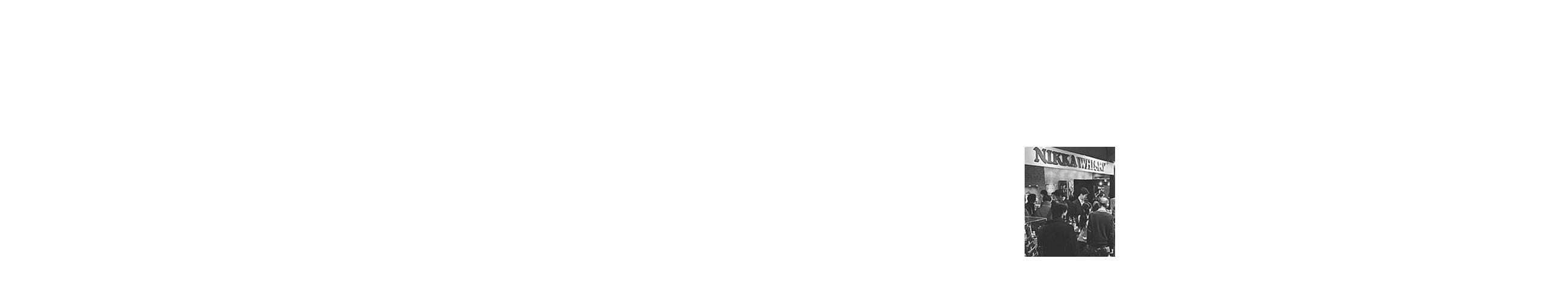第67話
第67話
麦溜(ばくりゅう)
先日、昭和44年頃にニッカウヰスキーに就職した社員の数人が定年退職されるということで挨拶に来られた。昭和44年といえば宮城峡蒸溜所が竣工した年であり、ウイスキーの需要が伸びている時期でもあった。蒸溜所の披露パーティーの前に、敷地内を小山内工場長と一緒に自転車で巡回したのが、つい昨日の事のようである。
年齢を重ねると共に過ぎた歳月が早く感じられるようになる、というが、19世紀のフランスの心理学者、ポール・ジャネーは「人が感じる月日の流れ」や「過去を振り返った際の時の流れの早さ」に対する感覚は若いときは遅く、歳をとるにつれて短く早く感じるようになる、と説いた。
10才の子供が1年を感じる感覚は人生の10分の1であるが、50才の人が1年を感じる感覚は人生の50分の1となるので、10才の子供に比べて50才の人の方が5倍、時の流れを早く感じるということになる。簡単な数学だ。また、子供の頃は感受性が豊かなので見るもの、聞くものすべてが新鮮で、身の回りで起こることが豊富で月日が長く感じられる。しかし大人になると様々な事を経験しているので新しい感動が少ないため、早く月日が過ぎていくように感じられるのだとも言われている。
さて、今年も『ウイスキーマガジン・ライヴ!』が開催されたが、年々、来場者が増えており、ウイスキーづくりに携わる人間としては、大変、喜ばしい限りである。中でもウイスキーという洋酒のイベントに“能”が登場したというのは大変興味深いものであった。演目は「麦溜(ばくりゅう)」というもので、モルトウイスキー物語が題材である。物語は次のような内容であった。
18世紀、イングランドに併合されたスコットランドの山奥、重税に悩まされた酒職人(ウイスキーづくりをしている人々)たちは、幸せに暮らせる日々が来るようにと神に祈った。すると水源の祠を守っているという老人(麦溜の神)が現れ、酒づくりを伝授。必ず栄えると言い残し、樽開けのときに再び現れる約束して祠の陰に消えていく。
酒職人たちは老人の教え通りに酒をつくり、数年の後、祠に樽を差し出したところ、中からあの老人が現れ、酒づくりを賛辞。ウイスキーは「神の恵みを受けた命の水である」と語り、酒職人と共に最後の仕上げをする。古樽から馥郁とした香りが立つように天人が舞を舞い、老人は天下泰平、万民幸福、五穀豊穣を約束し、人々に酒を与えて明け方の雲間へ消えてゆくのだった。
ライヴでは一部が舞われたが、日本の伝統芸能である能にモルトウイスキーが取り入れられるとは、実に面白い。しかし、何故、ウイスキーなのだろう?と思ったのだが、今回のライヴで舞った演者の方々はモルトウイスキーが大好きだということで、なるほど、と納得した。
それにしてもよくぞ能に仕立てたものである。ウイスキーづくりやその歴史などを能で表現できるなど想像もしなかったが、さらにオペラやミュージカル仕立てにしてみたら、どんな感じになるのだろう。ウイスキーというものをよく知らない方々にも親しみを持っていただけるかもしれない。
「麦溜」という題目で思い出したのが、戦時中、政孝親父がウイスキーの呼称を“麦溜”にしたらどうか、とラベルまでつくっていたことだ。当時、敵国の言葉を使ってはいけない、ということで野球の「ストライク」を“よし”、「ボール」を“だめ”と呼んでいたり、米国の地名などを用いた社名は日本語のものに変更させられたりしていた。そのため「ウイスキー」という表記も禁止されるだろうと考えて“麦溜”にしたようである。そうこうしているうちに終戦を迎えたため、わざわざ用意したラベルを使うことはなかった。
大麦を原料につくられるビールは「麦酒」。大麦麦芽を原料に、さらに蒸溜してつくられる酒がウイスキー。今回、「麦溜」という能の演目が誕生したことで、懐かしい出来事が思い出された。横文字が主流になりつつある今日この頃であるが、こんな時代だからこそ敢えて“麦溜”というラベルが貼られたウイスキーを販売したら、好奇心から飲んでくださる方々がいらっしゃるかもしれない。