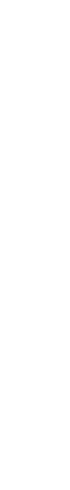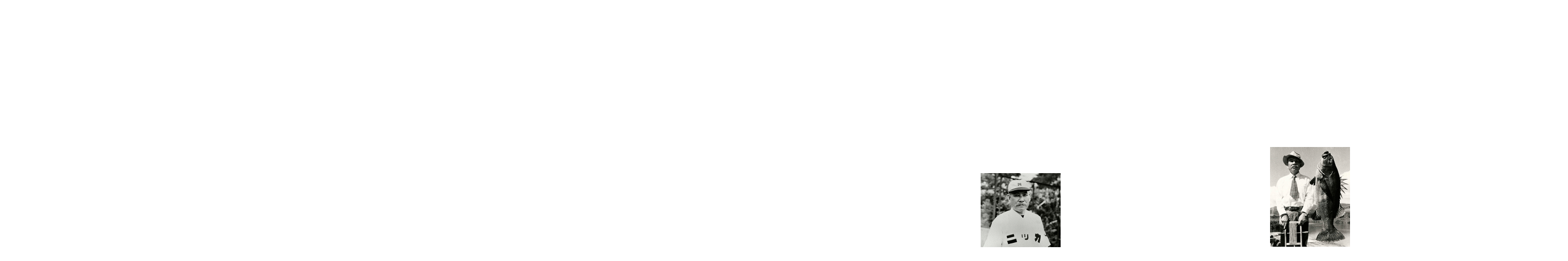第35話
第35話
遊びの精神
「よりよく遊ぶ者は、よく仕事をする」「良い酒をつくろうとする者は、口に贅沢させねばならない」という遊びの精神は、政孝親父が、ウイスキーづくりと共にニッカウヰスキーに残した伝統のようなものである。
創立記念日には従業員の家族も招いて余市蒸溜所の庭で大宴会を開いたり、船に鍋釜を積んで積丹半島まで繰り出し、政孝親父が釣った魚で磯鍋を楽しんだこともあった。余市川河口から約4㎞上流にある“あゆ場”では、政孝親父とリタおふくろが一緒に鮎釣りを楽しむこともあり、釣った鮎は自宅に持ち帰り、皆で食べたが、とても美味しかった。
また、積丹半島の先の海ではオウヨと呼ばれる巨大な魚が釣れることがあった。政孝親父はこれに挑戦。5年目にして大きさが1m10㎝、32㎏の大物を釣り上げたのである。これを刺身や鍋にして全従業員に振舞ったが、脂がのっていて、とても美味しかった。
一方、スポーツも大好きで、野球やテニス、スキーのジャンプ競技、柔道、剣道では「竹鶴杯」大会を開くこともあった。これは政孝親父が還暦を迎えたときに、余市町民のスポーツ振興のために寄贈したもので、現在も余市スキー連盟主催の「ニッカ杯」・「竹鶴杯」・「笠谷杯」それぞれのジャンプ大会が開催されている。このジャンプ競技にはさまざまなエピソードと思い出が残っている。
戦時中のこと、政孝親父は余市中学校の校長から「スキーのジャンパーは優秀な飛行士になる。空に舞い上がるという経験が飛行訓練に効果的なので、余市に中学生用のジャンプ台をつくって欲しい」と話を持ちかけられた。政孝親父は快く引き受け、早速、余市高校の裏山にジャンプ台をつくらせた。そして1941年、小樽市のジャンプ・元オリンピック選手、秋野武夫氏の設計で、余市中学校スキー部員たちによる夏休みも返上しての奉仕作業もあって完成。11月29日、台開きが行われたのである。
このジャンプ台は「竹鶴シャンツェ」と呼ばれ、後に笠谷幸生選手<※>を輩出。政孝親父は笠谷選手の金メダル獲得を大変喜んで、子供のジャンパーを育てようと「笠谷シャンツェ」(K30m級)を併設した。ここで船木和喜選手や斎藤浩哉選手らが育ち、余市町はジャンプ競技の盛んな町として知られるようになったのである。人口2万数千人の町から冬季オリンピックの金メダリストが3人も誕生する、というのはまさに快挙。長野の時はもう故人であったが、生きていたら、たいそう喜んだに違いない。
※1972年の第11回・冬季オリンピック札幌大会で行われた70m級ジャンプで、当時、ニッカウヰスキーの社員であった笠谷幸生選手が、見事、金メダルの栄冠に輝いた。
2000年にはジャンプ台の下を流れるヌッチ川の改修により場所を200m移動し、サマージャンプや夜間ジャンプも可能になった。これからも多くの若者が練習を積んで、いつか空高く羽ばたいていって欲しい。ウイスキーづくりに夢をかけた政孝親父のもうひとつの夢は、これからも受け継がれていくに違いない。
共によく働き、よく遊んだ社員のひとりに、ニッカウヰスキー前社長・宇野正紘氏がいた。彼は日本有数の蝶のコレクターで、北海道大学農学部時代には対馬、屋久島、奄美大島に生息する蝶を採集したこともあったそうだ。「どうしてニッカに入社したのか?」と尋ねたとき、彼は半ば冗談交じりにこう答えた。「蝶々追っかけていても食べていくことができないので」。
余市蒸溜所の独身寮で鳩を飼っている社員がいるかと思えば、かたや蝶の蒐集。「可愛くてたまらない」と芋虫を肩にのせていたりするほど蝶が大好きな男であった。
また、「良い酒をつくろうとする者は、口に贅沢させねばならない」という政孝親父の信条をそのまま実践していたのも宇野氏であった。料理はプロ級の腕前で、ウイスキーづくり同様、旨い物を食するということに対して寸分の妥協もなかった。かといって食通ぶることはなく、お得意様や従業員に手料理を振舞い「美味しい!」と大好評であった。
その宇野氏が5月27日、亡くなった。昭和38(1963)年入社。直接、ウイスキーづくりに携わってきた技術系出身で、宮城峡蒸溜所の立ち上げのときはウイスキーの仕込作業に明け暮れていた。十数年後、数十年後、熟成の眠りから覚めるウイスキーたちを夢見ながら無色透明の原酒を樽に詰めたウイスキーは、熟成を重ね、ニッカウヰスキーとして世に旅立っていくのである。ご冥福を祈ると共に、素晴らしいウイスキーづくりに尽力されたことに深く感謝の意を示したい。