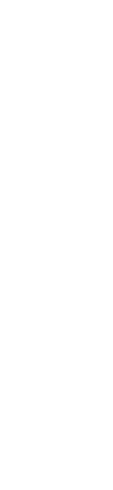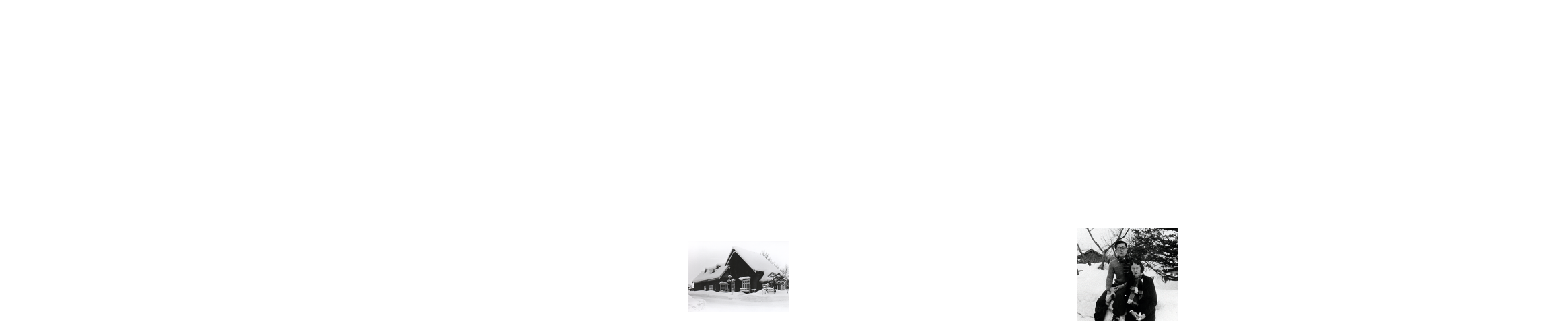第9話
第9話
余市での様々な出来事がはらはらと、白い雪と共に浮かんでくる
寒さが厳しくなり、東京でも雪が舞うようになると余市の雪景色が思い浮かぶ。
私が余市へ政孝親父とリタおふくろのところへ養子に行った頃は、シャン、シャン、シャンと鈴の音を立てて蒸溜所の中を馬ソリが行き来していた。250リットルの樽を4個も5個も積んで、随分と力持ちだと感心したものだ。屋根に積もる雪はある程度の量になると自然に下へと滑り落ちていた。蒸溜所が出来た当初、政孝親父は屋根から落ちた雪をそのままにしていたが、ある日倉庫の柱がわずかに歪んでいることに気がついた。どうやら倉庫の間に落ちた雪が建物を圧迫しているらしい。これではいけない、と屋根の雪下ろしと倉庫の間に落ちた雪を移動させるようになったという。この雪下ろしが大変だ。金属のスコップでザクザクとやってしまうとトタン屋根に穴を開けないとも限らない。当時は軽いプラスチックのスコップなどなかったので「じょんば」という木のスコップで雪下ろしや雪かきをしていたものだ。
当時私が政孝親父達と住んでいた山田の家は屋根の傾斜が急だったので雪下ろしをすることは殆どなかったが、それでも軒下に落ちた雪が積もると窓から外が見えなくなってしまうので、軒下や庭の雪かきは欠かせなかった。余市に来て初めての冬、天井がめりめりと軋む音で目が覚めた。そして次の瞬間、ドドーンという轟音が響いた。慌てて飛び起きたが、嘘のように辺りは静まり返っている。一体何事だったのかと首を傾げたが、あとで聞けば暖房の熱で天井があたたまり、やがて屋根に積もった雪が解け、ひと塊になって軒下に落ちた音だったのだ。確かに部屋には真っ黒な石炭ストーブがあり、凄まじい音を立てながら燃えているのだから、天井近くの温度が高くなるのは当然だ。しかし眠る頃には火種が尽きて明け方にはすっかり部屋が冷えてしまう。政孝親父は(髪がなくて)寒いので、手ぬぐいを頭に巻いて寝ていた。
余市の雪はリタおふくろの心配の種でもあった。雪は静かに降って規則正しく積もるものではない。吹雪いて吹き溜まりを作り、あちこちに瘤のような塊が出来上がる。ゴム長靴の膝の辺りまで積もっていると思って歩いていると、突如腰の辺りまで埋もれてしまう。雪を手でかき分けながら前に進んでいくので、よく「雪を漕ぐ」という表現をしたのだが、全くその通りだ。また、蒸溜所への行き帰り、狭い木の橋を渡るのだが、欄干の辺りまで雪が積もるので油断すると川に落ちかねない。私の帰りが遅くなるとリタおふくろは「川に落っこちたのではないかと心配した」と口癖のように言った。今となっては考えられないが、よくも毎日雪の中通ったものだ。
雪に悩まされることも多いが、同時に雪はニッカウヰスキーの恩人でもある。再溜釜マンホールのボルトに小さな穴が出来ていたためにボルトで締め付けたにもかかわらず溜出液が漏れ、引火。木骨石造建築の蒸溜棟は石壁を残して焼け落ちた。だが不幸中の幸い、降り積もった雪が窓を塞いでいたため延焼を免れることが出来た。この事故のせいで新しい蒸溜釜ができてくるまで作業は中断された。しかしこれが教訓となり、貯蔵庫の間には溝が掘られ、隧道(トンネル様のもの)を経て余市川に流れるよう工事がなされたのである。
雪、といえば南極探検隊の方々のためにウイスキーをつくったことがあった。アルコール度数40度前後のウイスキーはマイナス20度ぐらいでシャーベットになってしまう(南極の気温はマイナス40度近くまで下がる)。そこで飲用アルコールを混ぜたアルコール度数が70度のウイスキーをつくった。ビンでは割れてしまうので200リットルのドラム缶に詰めて送った。想像を絶する寒さの中、アルコール70度のウイスキーは彼らの慰めになったであろうか・・・・。
冬、寒さが厳しくなると、余市での様々な出来事がはらはらと、白い雪と共に浮かんでくるのである。