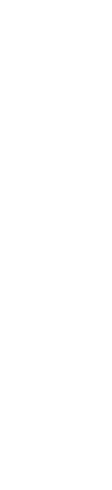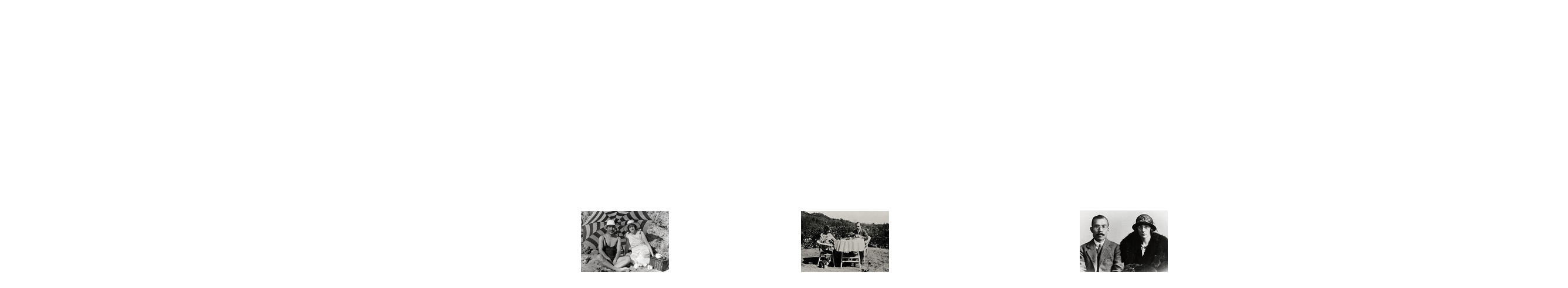第8話
第8話
IN LOVING MEMORY OF RITA TAKETSURU
昭和30年代に入り、好景気の波の後押しもあってウイスキー(『ブラックニッカ』『丸びんニッキー』など)は売り上げをどんどん伸ばしていった。景品につけたグラスは想像以上の反響があり、後に発売される『ハイニッカ』にもグラス=ハイグラスがつけられることになった。
ハイグラスはブランデーグラスを小ぶりにしたものに足があるもので、ウイスキーの水割り、オンザロックと用途が広く大好評。デザインも洒落ていた。これは私がヨーロッパに旅行したときによく見かけたグラスからヒントを得たものだった。サンプルをヨーロッパから取り寄せ、グラス会社に発注。足を機械でつけることが出来たので大量生産が可能になったのだが、当時としてはこの作業は画期的なものだった。
1957年(昭和32)には『ニッカベアー』(特級)を発売。熊の頭の形をしたキャップが付いたもので、この年から変形ビンを用いたギフト商品が販売されるようになった。『クリスタル』『シェーカー型』『ドリーム』『グランド』『62型』『ボウリング』。いずれも個性溢れるデザインのものであった。
ウイスキー市場の拡大と共に会社も順調に業績をあげていった。私も政孝親父も帰宅が遅くなる日が多くなっていった。リタおふくろは私の妻である歌子とお喋りをしたり、孫の面倒を見たりで気を紛らわせていたのかもしれない。しかし異国での生活に無理があったのか、体はあまり丈夫ではなく、冬の間は神奈川県逗子にある家で静養し、夏は余市で過ごすという生活を送った。リタおふくろは飛行機が苦手で行き帰りは必ず列車。一度だけ飛行機に乗ったことがあったが「足元が落ち着かなくて気持ち悪い。飛行機は、もうこりごり」と、二度と飛行機に乗ろうとはしなかった。そんな生活が続き、おふくろは60歳を過ぎてから入退院を繰り返すようになった。
12月のひどく冷え込む夜、庭から歌声が聞こえてきた。病床にいるリタおふくろを励ますために、余市教会の牧師さんらが来て、庭で賛美歌を歌ってくれていたのだ。「せっかく来てくださったのだから、家にあがって温まって行かれたら」と勧めたのだが、彼らは「お気持ちだけで。私たちはリタさんがよくなられるように、お祈りのための歌を歌いに来ただけですから」と帰って行かれた。あとでよく話を聞いてみたところ、その牧師は偶然にも私と同じ広島の福山出身で、中学の後輩でもあった。
12月14日はリタおふくろの誕生日で、おふ くろに「何か食べたいものは」と聞くと「おにぎりが食べたい」と答えた。そこで私はおふくろのためにおにぎりを握った。おかずは魚の刺身。にぎやかではなかったが、誕生日を祝うことが出来たことを嬉しく思ったものだ。
そして1961年(昭和36)1月17日、1カ月前に64歳の誕生日を迎えたばかりのおふくろは、余市の自宅で静かに最期を迎えた。肝硬変だった。亡くなった後2日間、政孝親父は自分の部屋に閉じこもりきり。葬式の準備を進めなければならないのに一歩も出てこない。人前で決して涙を見せない親父のこと、独りきりで泣いていたのではなかったか。「自分がウイスキーづくりをスコットランドで学び、グラスゴー郊外のカーカンテロフという町で知り合った “カウン家”のリタを日本に連れて帰ることが無かったら。もしかしたら彼女はこんなに早く亡くなることはなかったかもしれない・・・・」そんな思いが政孝親父の脳裏で渦巻いていたに違いない。
火葬場にも「俺は行かん」と言って骨を拾いにはいかず、九谷焼の香炉を持ってきて「ここに孫と一緒にひとつずつ、四つ骨を拾ってくればいい」と言い、言うとおりにしてそれを家に持ち帰ると、政孝親父はそれを床の間において墓が出来るまでずっと骨の入った香炉と寝食を共にしていた。
工場と余市川を見下ろせる美園町の墓地に、キリスト教式の墓が完成したのは一年後だった。政孝親父はいつまでも一緒にいられるようにと墓石に自分の名も刻ませ「俺が死んだら日付だけを入れればいいから楽だぞ」と笑った。しかし墓参りには行く気持ちにはなれなかったのだろう、工場から美園の丘に向かって軽く手を振ったりしていた。
墓石の裏にはこんな言葉が刻まれていた。
「IN LOVING MEMORY OF RITA TAKETSURU」