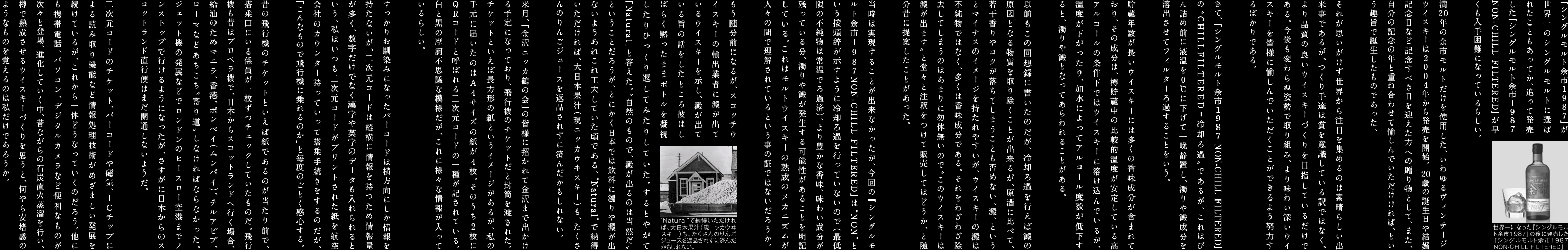第71話
第71話
シングルモルト余市1987 NON-CHILL FILTERED
『シングルモルト余市1987』が世界一のシングルモルトに選ばれたこともあってか、追って発売した『シングルモルト余市1987 NON-CHILL FILTERED』が早くも入手困難になっているらしい。
満20年の余市モルトだけを使用した、いわゆるヴィンテージウイスキーは2004年から発売を開始。20歳の誕生日や結婚記念日など記念すべき日を迎えた方への贈り物として、また、自分の記念の年と重ね合わせて愉しんでいただけければ、という趣旨で誕生したものであった。
それが思いがけず世界から注目を集めるのは素晴らしい出来事であるが、つくり手達は賞を意識している訳ではなく、より品質の良いウイスキーづくりを目指しているだけである。今後も変わらぬ姿勢で取り組み、より味わい深いウイスキーを皆様に愉しんでいただくことができるよう努力するばかりである。
さて、『シングルモルト余市1987 NON-CHILL FILTERED』の“CHILLFILTERED=冷却ろ過”であるが、これはびん詰め前に液温を0℃に下げて一晩静置し、濁りや澱成分を溶出させてフィルターろ過することをいう。
貯蔵年数が長いウイスキーには多くの香味成分が含まれており、その成分は、樽貯蔵中の比較的温度が安定している高アルコールの条件下ではウイスキーに溶け込んでいるが、温度が下がったり、加水によってアルコール度数が低下すると、濁りや澱となってあらわれることがある。
以前もこの回想録に書いたのだが、冷却ろ過を行えば澱の原因となる物質を取り除くことが出来るが、原酒に比べて、若干香りやコクが落ちてしまうことも否めない。澱、というとマイナスのイメージを持たれやすいが、ウイスキーの澱は不純物ではなく、多くは香味成分である。それをわざわざ除去してしまうのはあまりに勿体無いので“このウイスキーは澱が出ます”と堂々と注釈をつけて販売してはどうか、と随分昔に提案したことがあった。
当時は実現することが出来なかったが、今回の『シングルモルト余市1987NON-CHILL FILTERED』は“NON”という接頭辞が示すように冷却ろ過を行っていないので(最低限の不純物は常温でろ過済)、より豊かな香味、味わい成分が残っている分、濁りや澱が発生する可能性があることを明記している。これはモルトウイスキーの熟成のメカニズムが人々の間で理解されているという事の証ではないだろうか。
もう随分前になるが、スコッチウイスキーの輸出業者に澱が出ているウイスキーを示し、澱が出ている旨の話をしたところ彼はしばらく黙ったままボトルを凝視したりひっくり返してみたりしていた。するとやがて「Natural」と答えた。“自然のもので、澱が出るのは当然だ”ということだろうが、とにかく日本では飲料に濁りや澱が出ないようあれこれ工夫していた頃である。“Natural”で納得いただければ、大日本果汁(現ニッカウヰスキー)も、たくさんのりんごジュースを返品されずに済んだかもしれない。
来月、「金沢ニッカ鶴の会」の皆様に招かれて金沢まで出かける予定になっており、飛行機のチケットだと封筒を渡された。チケットといえば長方形の紙というイメージがあるが、私の手元に届いたのはA4サイズの紙が4枚。そのうち2枚にQRコードと呼ばれる二次元コードの一種が記されている。白と黒の摩訶不思議な模様だが、これに様々な情報が入っているらしい。
すっかりお馴染みになったバーコードは横方向にしか情報を持たないが、二次元コードは縦横に情報を持つため情報量が多く、数字だけでなく漢字や英字のデータも入れられるという。私はいつも二次元コードがプリントされた紙を航空会社のカウンター持っていって搭乗手続きをするのだが、「こんなもので飛行機に乗れるのか」と毎度のごとく感心する。
昔の飛行機のチケットといえば紙であるのが当たり前で、搭乗口にいる係員が一枚ずつチェックしていたものだ。飛行機も昔はプロペラ機で、日本からスコットランドへ行く場合、給油のためマニラ、香港、ボンベイ(ムンバイ)、テルアビブ、ローマなどあちこち“寄り道”しなければならなかった。ジェット機の発展などでロンドンのヒースロー空港までノンストップで行けるようになったが、さすがに日本からのスコットランド直行便はまだ開通しないようだ。
二次元コードのチケット、バーコードや磁気、ICチップによる読み取り機能など情報処理技術がめざましい発展を続けているが、これから一体どうなっていくのだろう。他にも携帯電話、パソコン、デジタルカメラなど便利なものが次々と登場、進化していく中、昔ながらの石炭直火蒸溜を行い、樽で熟成させるウイスキーづくりを思うと、何やら安堵感のようなものを覚えるのは私だけであろうか。