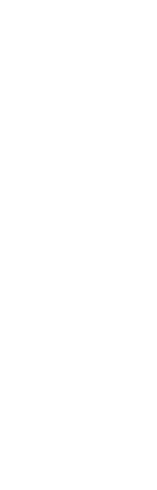第5話
第5話
弁当と味噌汁は温かく、おふくろのぬくもりが感じられるものであった。
数年前、余市の実家で荷物の整理をしていたとき、高さ30センチ位の壺が見つかった。何が入っているのだろうと開けて見ると表面に塩の結晶ができた梅干が少し残っていた。リタおふくろが漬けたものだ。おふくろが亡くなって33年が経ち、晩年は東京と余市を行き来していたので、作る機会はなく、間違いなく40年以上も前のもので、まさに稀少品。私は幾つかをガラスビンに入れ大切に持ち帰ったのだった。
日本人になりきろうとしたおふくろは、言葉はもちろん、料理もかなり勉強したようだ。政孝親父は晩酌の時は日本酒を好んだため、それにあうつまみを数々作った。沢庵好きの親父のために秋になると1年分の沢庵、三百数十本を4斗樽、2斗樽に漬け込んだ。ヌカと塩の按配も良く、とても美味しかったのを覚えている。また、英国料理もいろいろと作った。スコッチブロスという肉から出汁をとった野菜のスープやシェパードパイ、ローストビーフ。ブランデーをたっぷりきかせたクリスマスプディングは半年も前から作り寝かせておいてクリスマスに蒸しあげた。耳慣れないものだが、ゴールデンプディングも、よく作ってくれた。パンを粉にしたものにマーマレードを入れて蒸かしたものだが、名前どおり色は美しい金色。これが紅茶によくあった。休日ともなれば家族そろってアフタヌーンティーを楽しむ。
「それだけ食べて、よく太りませんでしたね」と言われたことがあったが、確かにおふくろの手料理は美味しく、たくさん食べていた。しかし余市にいる頃は太ることなどなかったのに、東京に転勤になった途端に体重が増えた。その原因は空気にあったのではないかと思う。東京の空気は酸素が少なく炭酸ガスが多い。エネルギーを消費するには酸素が不可欠なのだが、酸素が少ない空気の環境にいると、エネルギー消費量も少なくなり、結果脂肪が増える(太る)ことになったのではないかと思う。
おふくろにとって、何でも美味しい状態で食卓に出すことが喜びでもあり、じゃがいもなどは蒸かしたてで粉のふいたものが絶妙なタイミングで出てきた。また、工場にいる親父と私に弁当を毎日のように届けてくれた。片道1・5キロの道を40分かけて往復。弁当と味噌汁は温かく、おふくろのぬくもりが感じられるものであった。それだけに「家で食事をする」と時間も約束しておいて、帰宅が遅れたりすると大変御機嫌が悪かった。
帰化して日本人になりきっていたおふくろだが、青い瞳と鳶色の髪は隠し様もなく、戦時中は元英国人ということで「敵国人」扱いされたこともあった。特高警察に見張られたり、子供に石を投げられたり。部屋に置いてあったラジオのアンテナから秘密の暗号を発していないかと探知機で調査されたり。スコットランドの家族とは連絡もとれず、母国英国と嫁ぎ先の国日本が戦争状態にあることに、どれほど胸を痛めたであろう。敵国語である英米語の使用禁止、音楽、文化も迫害を受けていた。しかし酒は特別なのか、海軍の指定工場となり、英国の酒であるウイスキーの原料である大麦を支給され、原酒の貯蔵が途切れるという憂き目に遭う事はなかった。逆に本場スコットランドでは戦時中、原料難から仕込みが途絶えた蒸溜所もあったという。戦後、平和が訪れてもおふくろは当時の話をしたがらなかった。
慈母のように愛情深い人だった。スコットランドの母親とも頻繁に手紙のやり取りをしていた。繰り返し、繰り返し、その手紙を読んでいたが「帰りたい」と言ったり愚痴をこぼすことは決して無かった。
私は春から秋までは工場まで自転車で通っていたが、冬は雪の中を歩いて通った。必ず余市川に架かる橋を渡らなければならないのだが、当時はコンクリートではなく木製の橋。車一台通れる位の幅しかなく、欄干の高さまで雪が降り積もる。帰りが遅くなるとおふくろから「おまえがあの橋から足を滑らせて川へ落っこちたんじゃないかと心配した」と言われたことがあった。今思えば笑い話のようだが、おふくろにしてみれば心配の種だったに違いない。工場と家の往復の毎日。それを陰で支えてくれたのはおふくろであった。
そんな折、私に見合い話が持ち上がった。1度目は東京で紹介されたのだが縁がなく、2度目は1950年の春であった。