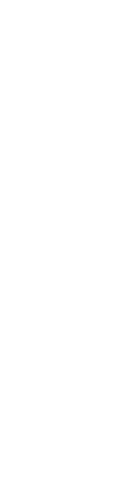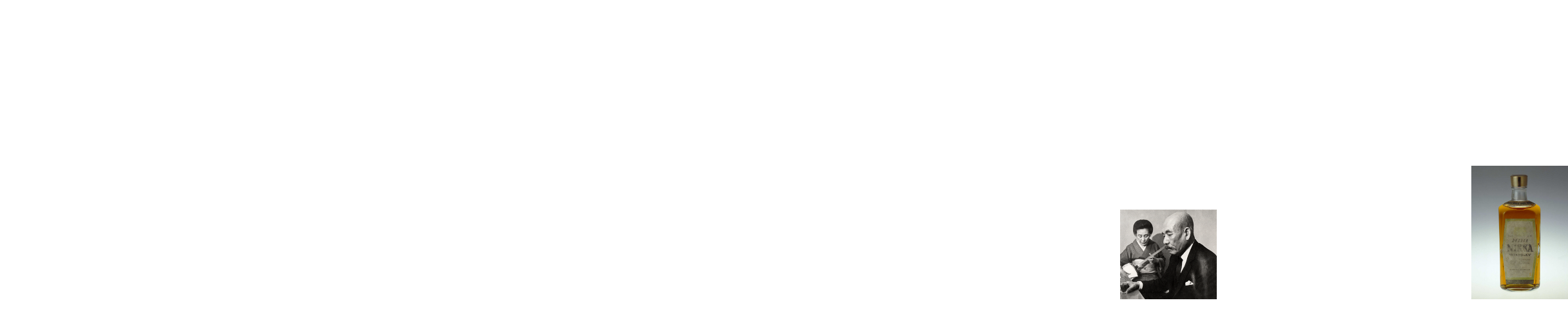第17話
第17話
東京オリンピックの年、時代は500円ウイスキーに沸いた。
スーパーニッカが発売されて2年後の昭和39年2月、500円ウイスキー・『ハイニッカ』が発売された。二級では初のアルコール度数39度、酒税法の上限までモルト原酒を入れた、まろやかな味わいのウイスキーは好評を博した。
当時は酒税法によって、特級、一級、二級と「級」で分けられており、特級は43度以上、一級は40度以上43度未満、二級は40度未満と度数によって決められていた(1989年の酒税法改正によって級による分類は廃止)。少しでもアルコール度数がオーバーすると税金も跳ね上がる。私は「酒税法がウイスキーの品質の向上を抑えているのではないか」と常々憤りを感じていたものだ。
この『ハイニッカ』、初代のラベルを見ると“HIHI”ハイハイになっている。政孝親父は、『ハイハイニッカ』という商品名で販売したいと思っていたのだった。実は「ハイハイ」は「ハイファイ」を呼びやすくしたもので、当時経済の高度成長と共に音響機器の改良も進んで、「ハイファイという言葉が飛び交うようになっていた。「ハイファイ」というのは「high fidelity」の略で、オリジナルの音に忠実であるというのが本来の意味らしい。「ニッカ(のウイスキー)ください。ハイハイ!というリズム感もあっていいじゃないか」と政孝親父は随分と気に入っていたようだが、やはり呼びにくいということで『ハイニッカ』におさまったのである。
政孝親父は他にも風変わりなネーミングを商標登録していた。なかには“長万部”というものもあった。「おしゃ・まんべー、という音が面白いじゃろう」と笑っていたが、結局、日の目を見ることはなかったのである。
昭和39年といえば東京オリンピックが開催された年で、景気も良かった。そのせいかどうか500円というジャストプライスがうけていた。細かいお釣りが要らない手軽さが良かったのだろう。不景気になると端数をつけて少しでも安いイメージを持たせるものだが、価格にも時代背景が反映されるのであろう。オリンピックが開催される前年に、カフェグレーン設備の買い付けにスコットランドへ行った帰り香港に寄ったのだが、イタリア人のタクシー乗務員に「日本はもうオリンピックが開催されるんですね。全く凄い国だ」と言われたのが思い出される。
時代は500円ウイスキーに沸いた。そこで、より売り上げを伸ばすために『ハイニッカ』に景品をつけて発売することになった。当時、ウイスキーにはよく景品がついており、それによって売り上げが決まるといっても大袈裟ではなかったのだ。
私の脳裏に浮かんだのはヨーロッパを訪れたとき、よく目にしたグラスで、ウイスキーはもちろんワインやブランデーを飲むときにも使える、まさに万能グラスだった。ブランデーグラスを小ぶりにした、足つきのもの。ヨーロッパに出張した社員に、そのグラスを持ち帰らせて、早速、グラスメーカーに似たようなグラスを発注したのだった。当時、自動機械で足つきのグラスを完成させるのは画期的なことであった。
「ハイグラス」と名付けられたそれは、約7オンス(210㎖)グラスで、一際、目を引いた。お陰で『ハイニッカ』は飛ぶように売れ、ハイブームを巻き起こしたのだが、以来、支店長会議ともなると話題の中心は景品ばかりで(私たちはウイスキーを売っているのであって、景品を売っているのではない)と、いささか辟易したのも事実である。
政孝親父はハイニッカが大のお気に入りで、毎晩のように飲んでいた。「皆、さぞかし竹鶴政孝は高価なウイスキーを飲んでいるに違いないと思っているだろうが、わしは一番売れているウイスキーを飲むんじゃ!」そう言い続けた政孝親父。実は親父が一番の『ハイニッカ』ファンだったに違いない。