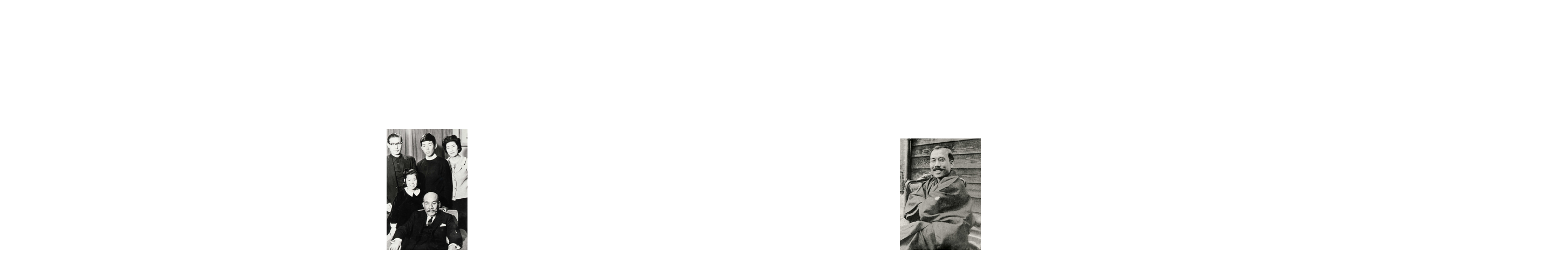第15話
第15話
ときどき「わしは幸せ者じゃ・・・・」と呟いていたものだ
8月になると思い出すことが幾つかある。広島、長崎への原爆投下、第二次世界大戦の終焉。そして政孝親父が静かに迎えた最期の日、8月29日は親父の命日である。ウイスキーづくりに命をかけた人生であったが、同時に“やりたいこと”は全部やり尽くした充実した人生ではなかったか。ウイスキーづくりの夢を携えて英国に渡り、英国人の伴侶と共に帰国、試行錯誤をしながらも政孝親父の夢は蒸溜所と貯蔵庫の数が増えるごとに実現していった。晩年、ときどき「わしは幸せ者じゃ・・・・」と呟いていたものだ。
蒸溜所の敷地内にある会館で、ハタハタや鮭など余市の新鮮な海の幸を使った鍋パーティーをよくやったものだ。当時は100名以上の従業員がいたのでとても賑やかだった。NHKの、のど自慢大会に出たこともある歌の上手な従業員に「おい、歌を歌ってくれ」と政孝親父が顔をほころばせながら言う。お気に入りだったのは「雪の降る町を」「アカシアの雨がやむとき」。もちろんカラオケなどは無く、伴奏も無かったので皆がリズムをとるように手を叩くと、「せっかく聞いているのに手拍子は邪魔になる。手を叩くなら聞き終わってからにしろ」と注意したこともあった。家に客人を招いたり、会食するときなどは「どんな料理を振舞うと喜んでくれるか。どんな話をしようか」と事前にあれこれ考えたりと、人をもてなすことが好きな人でもあった。
80歳を越えて、白内障の手術を受けてからあまり動き回らなくなり、1ヶ月ベッドに横たわっていたために足が動かなくなっていた。運動不足解消にとエアロバイクを購入したのだが、結局は三日坊主。視力矯正用のコンタクトレンズは「あんな面倒臭いもん、使えるか」と使わずじまいで眼鏡を作ったのだが、レンズがそれこそ牛乳瓶の底のように厚く、不自由であったのだろう。読書をすることはなくなっていた。
84歳になってから、東京の順天堂大学に入院してからはベッドから動こうとしなくなった。仕事はもちろん、ハンティング、釣り、海水浴、仕事の合間の囲碁、とじっとしていることのなかった親父が病院のベッドの上で日がな一日テレビを観ている様子に胸がしめつけられるような気持ちだった。それでもウイスキーは飲み続け、水で割ったウイスキーが吸い飲みに入れられ枕元に置かれている。医師もこれには諦めた様子で「空き瓶だけは病室に置かないように」と言われただけだった。無理に外出しようとすることもなく、政孝親父は病室で過ごしていたが弱音を吐くようなことは一度も無かった。病室にお見舞いの人が来るとカイゼル髭を蒸しタオルで整え、着物(和服)を着て迎えていた。着物といえば自宅にいるときも着物のことが多く、冬は紋付の羽織を羽織っていたのでお客が「政孝さんはわざわざ紋付をお召しになって出てこられた」と恐縮することがあったのだが、政孝親父の紋付の羽織は普段着のようなもの。色が褪せて茶色っぽくなっていても構わず着ていたものだ。
自分が死んだ後の事も、政孝親父らしく全部自分で決めていた。「遺体はマンションに運ぶな。近所の人たちに迷惑がかかる。もうわしはあそこに帰らんでもいい」「社葬は青山斎場になるはずじゃ。場合によっては麻布工場でもよい」「骨は美園の丘の墓に入れてくれ。骨壷はいらん。おまえたち夫婦と孫二人で香炉に入れてくれればよい」。
1979年6月20日は政孝親父の最後の誕生日だった。家族が集まり、政孝親父は「みんな来てくれたから、うな重を頼もう」と、うな重を出前でとった。「わしはあとでゆっくり食べるからおまえたち先に食べなさい」と孫たちに言う。孫たちが美味しそうに食べる姿を嬉しそうに笑いながらながめていたが、政孝親父は、もう食欲が衰えてしまっていたのだろう。箸をつけることはなかった。
8月29日、政孝親父は私たち夫婦に看取られて85年の生涯を静かに閉じた。死の直前、意識がなくなったときに洗礼を受け「アブラハム」というクリスチャンネームを授かり、リタおふくろの元へと旅立っていった。しばらくは話さずにいたのだが、政孝親父が亡くなると医師から遺体を解剖したいとの申し出があった。政孝親父の性分を考えて最初はお断りしたのだが、再三の要請があり承諾したのだった。その後医師から「肝臓はまだ大丈夫でした」と報告があり、ほっとしたのを覚えている。
葬儀の日、棺の中の政孝親父の唇をスーパーニッカで湿らせてお別れをしようとしていたところ、長男の孝太郎が私の手から瓶を取り上げ、1本まるごと遺体にかけてしまった。そのときの政孝親父の顔は、晩酌でウイスキーを飲んで微笑んでいるときの顔そのものだった。