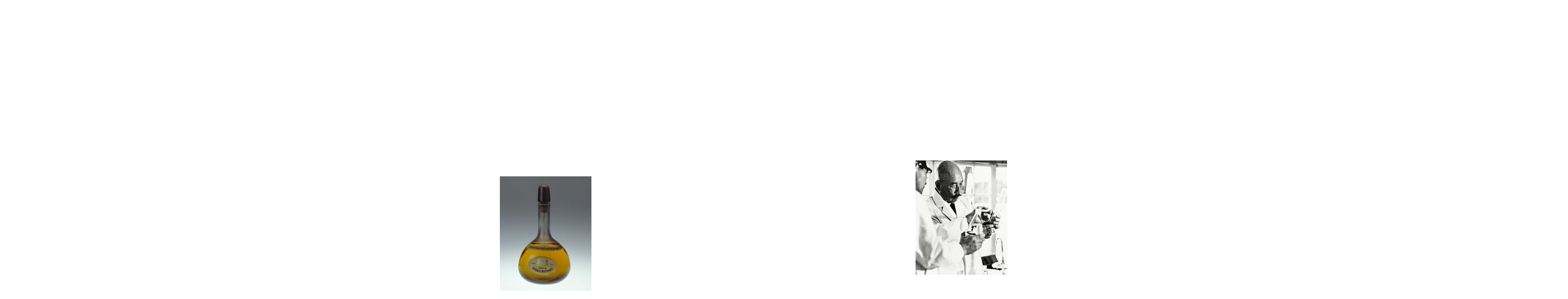第11話
第11話
嫁にやるのと一緒なのだから、立派な衣装を着せてやりたい
「スーパーニッカ」が販売されたのは昭和37年。早いものでもう40年が経った。戦後ウイスキーの多くは、ほとんどモルトが入らないイミテーションウイスキーであった。それでもつくれば飛ぶように売れていた。そんな時代に、政孝親父は余市のモルト原酒をふんだんに使った特級ウイスキーをつくり続けたのだった。しかし経営の必要上、三級ウイスキーをつくらざるをえなくなり、政孝親父は涙をのんで三級ウイスキーづくりに踏み切った。頑なに「わしゃ、絶対に三級ウイスキーなどつくらん!」、「あれじゃ、ウイスキーとはいえん」と言い張っていたのを今でも思い出すことがある。昭和28年には1、2、3級の級別が、特、1、2級に変わり、市場は2級を中心に伸びていた。「スーパーニッカ」は、そんな政孝親父の本物のウイスキーづくりに対する情熱そのものであり、リタおふくろを亡くしてショックを受けていた政孝親父を再び立ち上がらせてくれた原動力でもあったのだ。当時は5棟しかなかった貯蔵庫でサンプルを採り、研究室にこもり、私は政孝親父と一緒に新しいウイスキーづくりに励んだ。当時は設備もまだ現在ほど充実していなかったが、そのせいかどうか個性的な原酒が多かった。お陰で元気を取り戻した親父は、知人から勧められゴルフを始めた。シャフトがヒッコリーのクラブは、リタおふくろがスコットランドから持ち帰ってきたものだ。しかしリタおふくろが生きているときは一緒にプレーしたことはない。本場仕込みのリタおふくろは「シングル」であったらしいので、負けず嫌いの政孝親父はゴルフばかりは一緒に楽しむことがなかったのでは?と専らの噂であった。
いよいよ念願の新しいウイスキーが完成した。政孝親父は「ウイスキーが熟成するまでに何年もかかる。これは娘が大きくなれば嫁にやるのと一緒なのだから、立派な衣装を着せてやりたい」と言い、各務クリスタルにボトルづくりを依頼した。各務クリスタルは昭和30年に発売された「ゴールドニッカ」のボトルをつくっている。宙吹き成型(*)の後、カットを入れた豪華なものであった。ボトルをデザインしたのは佐藤潤四郎氏。独特の形は、中国の器からヒントを得たもので、ボトルの材質はセミクリスタルだった。手吹きなので栓の下とボトルの底に番号が刻まれており、これが一致しないと栓が閉まらない。お見事、と感心したのはラベルを貼る箇所だった。真っ赤に焼けたガラスを濡らした真新しい新聞紙に軽く滑らせて平らにする。古新聞では駄目なのである。あまり押さえすぎると平べったくなってしまうし、足りないとラベルがきちんと貼れない。あの何とも繊細な胴の膨らみは文字通り職人技。素晴らしい花嫁衣裳である。
しかしボトリングしてみて困ったのは容器の大きさの違いが多く、入れ目の不揃いであった。多く入っているように見えるものにはクレームはこなかったが、やはりびん上部に空白が多いものは「量が少ないじゃないか」とクレームがきた。容量は一緒なのだが、なにぶん手吹きなのでボトルの厚みがわずかに違う。そう説明してお客様に納得して戴いたのであった。720㎖入りで3000円。大卒初任給が15000円前後だった時代に随分と贅沢な価格設定だったが、それでも「飲みやすく味わいのあるウイスキー」と評判になり売れ行きも伸びていった。昭和39年、東京オリンピックが開催された年には5色のリングの色をガラスで出した「スーパーニッカ」の5本セットを限定販売した。価格は15000円。残念ながら私の手元には残っていないが、とても美しいボトルだった。
「スーパーニッカ」は順調に売れるようになったが、手吹きのボトルでボトリングも手作業で行わなければならず、大量生産は不可能だった。やがて昭和43年の酒税引き上げによって従価税率220パーセントの適用で多額の酒税がかけられることになった。ボトルがクリスタル製のためコストが高くつくため、当然価格も高いものになる。しかも輸出用酒として外国市場に出す場合、コスト的にもスコッチウイスキーと対抗することが不可能という難点もあった。結果「新スーパーニッカ」が誕生したのである。
*ガラス製品の中で型を使用せずに吹きだけで仕上げる製法。ひとつひとつが手作り品ということになる