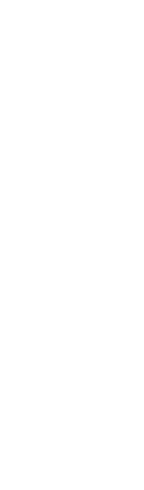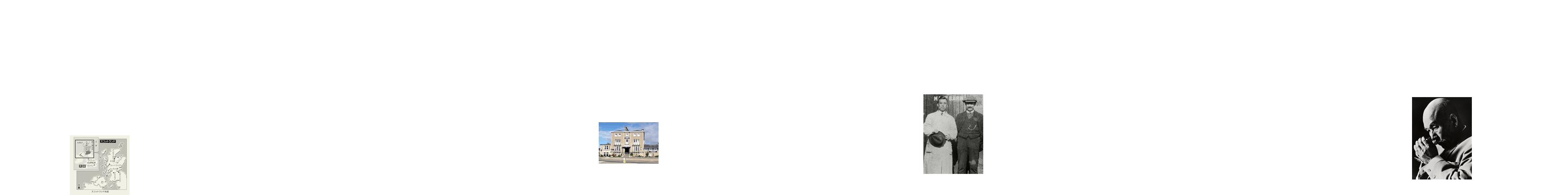旅立ち
第1回
旅立ち
「どんな仕事も新鮮」蒸溜所に飛び込み目と肌と鼻で学ぶ
ツテもなく渡英した24歳
ロンドンからスコットランドのインヴァネスまで飛行機で一時間四十五分。さらに車で一時間弱。スペイ川の河口近くにあるエルギンは、石造りの建物が並ぶこぢんまりとした静かな町だ。スコットランド全体のウイスキー蒸溜所の約半数が点在する“ウイスキー街道”の起点となる。
大正八(一九一九)年四月、二十四歳の竹鶴政孝は、この町から日本人で初めてウイスキー蒸溜所の実習へ向かった。いま、日本のウイスキーは世界の五大ウイスキーのひとつに数えられるようになった。それはわずか八十五年前、政孝がこの地に足を踏み入れた瞬間から始まった。
大正六年初春、大阪の摂津酒造で洋酒作りに携わっていた政孝は、阿部喜兵衛社長に呼ばれた。
「スコットランドに行ってモルト・ウイスキーの勉強をしてくる気はないか?いつまでもイミテーション(模造品)の時代じゃないし、品質にも限界がある。本場の技術を習得してきてほしいのだが」
政孝は社長の突然の申し出に、返事もできないぐらい驚いた。

自伝「ウイスキーと私」(日経新聞連載『私の履歴書』に加筆、ニッカウヰスキー発行)には、「メッカのスコットランドに技術者として留学できる喜びと、この若造を、しかも入社一年たらずの私のことをそこまで信頼してくださるのかという人間としての感動、その二つが交錯して、つきささるような感激が私を襲った」と、その思いをつづっている。
故郷・広島の両親を説得し、仕事の後任を決め…。その間にも、洋酒作りへの情熱はますます高まっていった。
翌年六月二十九日、神戸港を出発。
サンフランシスコ経由でぶどう酒作りを見学した後、十二月、政孝は英国のリバプール港に到着した。
出発から、はや半年が過ぎていた。
英国に上陸した政孝にウイスキー作りを学ぶためのツテは何もない。持っていたのは英語で書かれた大阪高等工業学校(現大阪大学)醸造学科の卒業証明書だけだった。
政孝はスコットランドにあるグラスゴー大学とロイヤル工科大学(現ストラスクライド大学)の門をたたく。この物おじしない体当たり精神が、後々まで政孝の人生をあと押ししていく。 グラスゴーは商工業の中心都市で、外国人も多かった。
グラスゴー大のマルコム・マクラウド副学長は「当時この町は、留学生を特別聴講生として積極的に受け入れていました。授業料も必要なかったようです。でも日本人は珍しく、タケツルで、三人か四人目の日本人聴講生でした」と説明する。現在、グラスゴー大学の日本人留学生は三十二人いる。
政孝は有機化学と応用化学を専攻する。初受講の日、ロイヤル工科大のフォーサイス・ジェームズ・ウィルソン教授が見なれない生徒に、「Are you Spanish?」と聞いた。
「No, I am not. I am Japanese.」
はっきり答えた政孝の大きなワシ鼻と意志の強そうな目は、英国人の持つ日本人の印象とは違っていた。

勢い込んで臨んだ講義には、日本で学んだ以上の内容はなかった。
図書館で関係書を読みあさる政孝に、ウィルソン教授は、「ウイスキー並びに酒精製造法」(J・A・ネトルトン著)という本を勧める。
政孝が帰国後もウイスキー作りのバイブルとして手放さなかった一冊だ。
何度も読みなおすうちに、政孝は著者に直接教えを請いたいと思い始める。ネトルトンは、エルギンに住んでいた。
四月、政孝はグラスゴーから汽車でエルギンに向かった。
駅前のステーションホテル(現レイクモレイホテル)に宿を求め翌朝、ネトルトンを訪ねた。
「本場のウイスキー作りを学びに日本から来ました。ぜひ指導をお願いしたい」
率直に切り出す日本人青年に、ネトルトンは答えた。
「実習をしたければ工場長に謝礼が必要です。二十ポンドほどあれば私が頼んであげてもいい。私の講義を受けたければ最初の月は二十ポンド。現金でいただきたい」
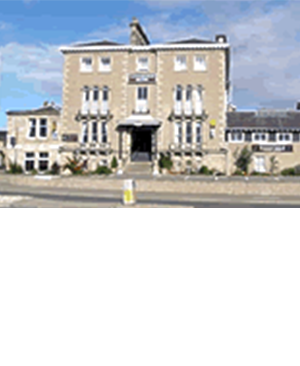
その料金が妥当なものかどうか分からなかったが当時、政孝の一カ月の生活費が二十ポンドから三十ポンドだった。
「留学生の私には高すぎます。払えません」
政孝の言葉を聞くと、ネトルントン家の扉は閉じられた。
ここまできてあきらめて帰るわけにはいかなかった。
幸い、スペイ川沿いには蒸溜所が数多くある。政孝はスコットランド・グレート・ノース鉄道(現在は廃線)に乗り、南へ五キロほどの最初の駅、ロングモーンで降りた。目の前にロングモーン・グレンリベット蒸溜所(現ロングモーン蒸溜所)があった。
ロングモーン蒸溜所は一八九四年創業、当初からその酒は高い評価を受けていた。
J・R・グラント工場長は「ウイスキー作りは本を読んだだけじゃだめ。体で覚えるものだ」と、初めて見る日本人の突然の訪問にもかかわらず、快く職人といっしょに働くことを受け入れた。
紹介料や謝礼は必要なかった。
一週間の“研修”で政孝は、「釜をたたいて反響で、蒸溜具合を知る」「最高のウイスキーは高価なシェリー樽(だる)で熟成する」など、書物では得られない体験をする。
だれもが嫌がる蒸溜釜の掃除も「なんとかして本格式のウイスキー作りの方法を身につけたい私にとって、どんな仕事も新鮮そのもの」と率先して引き受けた。
目と肌と鼻で学んだ一週間の経験は、「本物のウイスキーを作る」という信念をより確固たるものにした。そして、この「本物」へのこだわりは、政孝の一生の課題になっていく。

大学に戻った政孝は、ホームシックに悩まされながら図書館通いを続けていた。
そのころ、グラスゴー大医学部唯一の女子学生、イザベラ・リリアン(エラ)・カウンと知り合う。
「弟に武術を教えてほしい」というエラに誘われその夏、政孝はグラスゴーの郊外、カーカンテロフにあるカウン家を訪れる。
そこには、エラの姉、ジェシー・ロバータ(リタ)・カウンとの運命の出会いが待っていた。
=敬称略(田窪桜子)