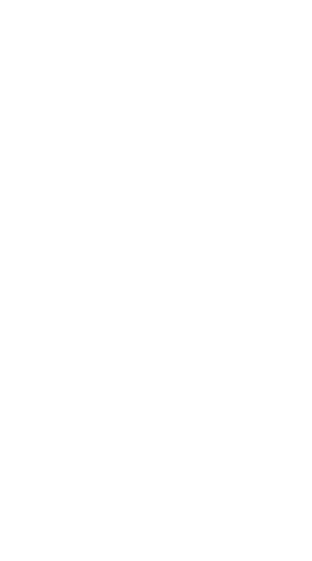竹鶴政孝物語 第2章
【第二話】
恵まれた出会いが夢を紡ぐ
先駆者とは孤独な存在である。
自分の前には何の道もなく、内奥からの声に、ひたすら耳をかたむけながら、自ら信ずるところを歩くしかないのだから―。愚直なまでに、ただ一心に。
たとえ人一倍強い自負があろうとも、艱難辛苦の代償として成功が約束されるわけではない。闇の中に一歩をふみだす情熱の裏に、不安が皆無とは言いきれまい。並外れた精神力に加え、事実を見据える技術者としての透徹した眼力が、琥珀色の英知を日本に根付かせる基となったのである。
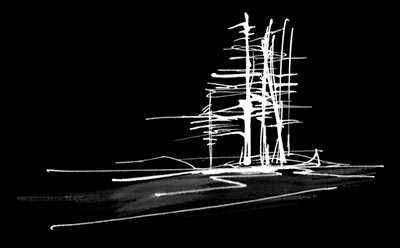
登記所結婚
インク壷からたっぷりと鵞ペンにインクをつけて、記帳台におかれた革装の帳面に署名した。カリカリと紙の上にペンを走らせながら政孝は、『前進あるのみ、この人と終生いっしょに夢の実現のために歩むのだ』、と心につぶやいた。
「リタ、君の番だよ」
政孝の渡したペンを微笑で受けとり、リ
タはためらいもなく一気に署名した。いつもは、湖のような神秘的で深く静かなリタの瞳が、雲間からさす陽光にキラキラ輝いている水面のような高貴さと、決意の色に染まっているのを見た。
一九二十年一月、グレート・ハミルトン街カールトンにある地区登記所は森閑としていて、この日はあたりに霧がたちこめ、寒さが厳しかった。妹のルーシー以外、立ち会いに家族の姿はなかった。竹鶴政孝二十五歳、ジェシー・ロベールタ・カウン、愛称リタ、二十三歳のときだった。
政孝がプロポーズしたのは、グラスゴーの少し北にある『明るく美しいほとり』とうたわれたローモンド湖畔。
「結婚してほしい、リタ。君が望むならここに留まる覚悟でいるんだ」
「いいえ、あなたには大望があるはずよ」
「……」
「わたしたちは、日本に行くべきです。絶対に」
毅然としながらも優美な感情を口許に浮かべて、リタはさとすように政孝に言った。家族や親戚の反対を押しきってなお、住み慣れた故郷を離れることも厭わないというこの女性に恋したことを誇らしくも切なく、そしていとおしく思った。この人を大切にしよう、北の空に誓ったことを回想していた。

夢の原型、キャンベルタウン
遠くスコットランドでウイスキーの製法を体得し「日本で本格的ウイスキーをつくるんだ」と熱く夢を語ったこの人についていこう。リタはリタで若き日の政孝の一途さに驚愕と恋慕の情を禁じえなかった。また、こうと信じたらどこまでも突き進む、洗練された野性もスコットランド氏族社会の勇士を彷彿させて好ましかった。
愛妻リタを伴って留学最後の仕上げを、キャンベルタウンのヘーゼルバーン蒸溜所で実習した。製法や設備、工場配置図、機械や部品の精密なスケッチ、はては職人の待遇、税金に関してまでもが精緻な記述で残された政孝のノートに、リタの内助の功、少なからざることが容易に読み取れる。リタは遅くまでノートの整理をする政孝の邪魔にならないように編み物をしたり、時折読解を手伝うことに無上の喜びを感じていた。
「マサタカ、もう寝ないと朝になりますよ」
「そうだね、リタ。ごめん」
キャンベルタウンはノース海峡をへだててアイルランドに面する半島に位置する港町。二人にとってこの町が、夢の原型となる揺りかごであった。
帰国
日本郵船〈伏見丸〉が横浜港大桟橋に接岸したのは、一九二十年もすでに秋色を濃くしていた頃であった。
「あなたのお国に、ついに来たのね」
期待と不安がリタの胸の中を駆けめぐり、出口を求めていた。察してか、政孝が甲板で外套にくるまった彼女を軽くひきよせた。
「いよいよ僕らのウイスキーがつくれるね」
答えのかわりに頭を政孝の肩にあずけたリタの髪からかすかにシャボンのかおりがした。
「リタの香りだ」
「昔、お母さまから頂いたのと同じなの」
リタはまだ、心のどこかでスコットランドの家族に詫び続けているのだろうか、政孝は遠くの山並みに眼をそらした。さぁ、私たちを待ち受けている未来の第一歩だ。政孝は本格ウイスキー蒸溜の青写真と愛妻を抱きかかえながら、タラップを一歩一歩ふみしめた。
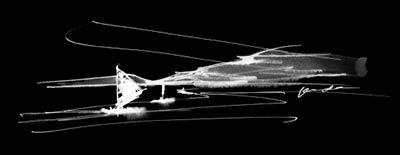
出会いそして別離
出会いとは不思議なものである。リタの弟ラムゼイが柔術を習わなかったら、二人は出会わなかった。そして、スコットランドで軒並み蒸溜所を訪ね歩いたことが寿屋(サントリー株式会社の前身)・鳥井信治郎の来訪を受けることにもつながったのだから。本格ウイスキーの到来を確信していた鳥井は、日本での製造にむけてウイスキーの権威、ムーア博士に技術指導の打診をしていた。
「日本には若くて優秀な、スコッチ・ウイスキーの技術者がいるではありませんか」
ムーア博士の意外な言葉に鳥井は驚いた。
「日本人でですか」
「そう、竹鶴政孝という青年です」
鳥井はウイスキーづくりを知っている唯一の日本人である政孝を好条件で遇した。
工場の建設にあたり、政孝は、敷地選定、工場および製造設備の設計などを指導し、工場設立後は、工場長としてウイスキーづくりに没頭する日々を過ごした。そして、一九二九年、ロングモーン蒸溜所研修から数えて十年目、日本初の本格ウイスキーを世に送りだした。
「あなた、おめでとうさん」
関西弁をまじえてリタが精一杯の祝福をした。
「やっとできた。ありがとうリタ、君のおかげだよ」
日頃、政孝の妻にふさわしくと、漬け物をつくったり関西弁を操るリタのけなげさに胸を熱くしながら、そのさしだした手の甲に接吻した。
夢にまで見た本格ウイスキーの発売だったが、さらなる理想のウイスキーづくりを目指し、政孝は約束の年限をもって寿屋を辞した。
鳥井の直感と理解なくしては実現困難であったろう日本での本格ウイスキーづくり体験は、政孝の新しい出発に覚悟とさらなる確信を与えるに十分な重みがあった。

不惑四十にて、まっさらからのスタート
一歩ちかづいたと思えば、また遠ざかる。終わりのない永遠の現在進行形、それがウイスキーづくりの道であり、竹鶴政孝が誇りをもって営々として歩んだ道である。
留学時代の記憶がよみがえる、体にしみ込んだ感覚が体の中心からめざめていく。北海道積丹半島の付け根、余市に立った政孝は武者ぶるいした。
「ここはスコットランドか」
ヘザーの花こそ咲いていないが、ながれる雲、かすかに湿った風のかおり、冷涼な空気も十分だ。足の下には無尽蔵のピートが広がり、清冽な水がこんこんと湧いているではないか。
「リタ、ついに見つけたぞ。僕らが夢を託せる理想の土地だ」
日本中を探し求めたすえに、行き着いた約束の地・余市は、政孝がたずね来るのを待っていたかのようであった。一九三四年、七月。『大日本果汁株式会社』設立。資本金十万円、敷地は四千五百坪。会社設立までの怒濤の日々を終えた政孝は、工場敷地内に建てた木造洋風家屋にリタを迎え入れ、ウイスキーの原酒をつくり始めた。蒸溜所の煙突からはピートを焚く青い煙りがたちのぼっている。青春の地、スコットランドの風土に酷似した余市で政孝の新たなる挑戦が始まろうとしていた。